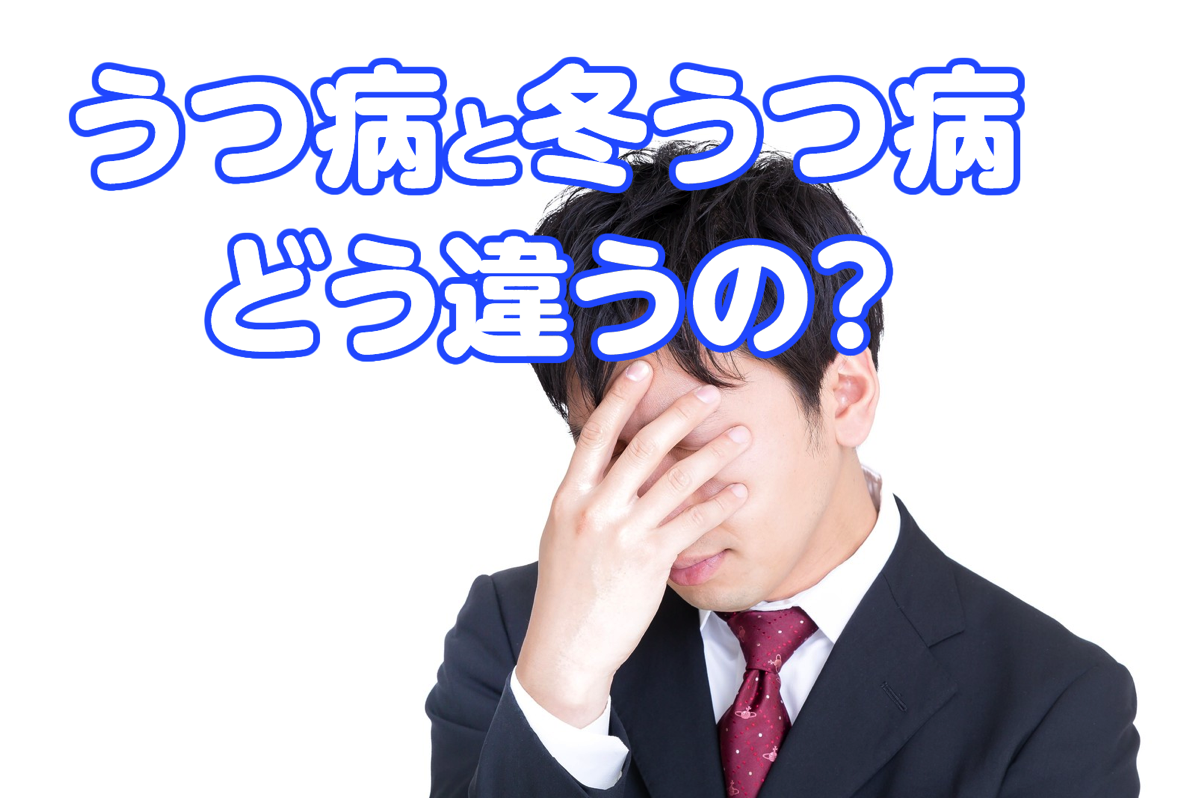冬うつ病とは「季節性感情障害」(季節性うつ病・冬鬱病・冬季うつ病・ウインターブルー)の一つで、1984年に米国の研究者が新しい病気として発表しました。
- 不眠または何時間寝ても起きられない、一日中眠い
- 炭水化物や甘いものを食べたくなり、体重が増える
- 不安感やイライラを感じる
- 夏場よりも首や肩のコリを感じる
- 集中力がなくなる
- 些細なことも面倒くさい
冬うつで、このような事を感じている方は、続きをお読みください。
パッと読む見出し
それって冬うつかも?
原因は【セロトニン】の不足だといわれています。
日照時間が短くなることで、睡眠ホルモン・メラトニンの分泌のタイミングが狂い、体内時計が狂ってしまう。安らぎホルモン・セロトニンの分泌量が減ります。
ホルモンバランスが崩れ、総合的に心身に影響を出してしまうのが『冬うつ』の特徴です。
「寒い」「曇りがち」というネガティブな環境もマイナス思考になりやすく、『冬うつ』を加速させてしまいます。
朝の『セロトニン=平常心』夜の『メラトニン=眠気』を知ろう!
☆睡眠ホルモン【メラトニン】とは?
メラトニンは太陽の光を浴びてから、約14〜15時間後に分泌が開始されます(体内タイマー)。
メラトニンは外が明るい間はほとんど分泌されず、夕方になり暗くなってくると分泌量が増えてきます。
夜、完全に太陽が沈むと、分泌量がさらに増えて、午前2時頃に分泌量がピークに達するという性質を持っています。
朝、目が覚める頃になるとメラトニンの分泌が止まり、太陽の光を浴びることにより、一気に体内のメラトニンの量が減少します。
メラトニンの量が減少することにより、脳が睡眠状態から覚醒状態へと切り替わるのです。
日照時間が短くなるとメラトニンの量が減少しにくく、日中眠い状態が続いてしまうわけです。
メラトニンがしっかりと分泌されると、アンチエイジングの効果もあります。
メラトニンは抗酸化物質の一つで、夜ぐっすり眠らせてくれると同時に、日中活動している間に発生してしまった悪玉物質「活性酸素」も処理してくれます。
☆安らぎホルモン【セロトニン】とは?
日照時間が短くなることで、安らぎホルモン・セロトニンの分泌量が減ります。
セロトニンは脳全体に影響を与える神経伝達物質で、ストレスによる脳疲労を防ぎ、精神を安定させたり、満腹感を与え過度な食欲を抑えたり、集中力を増進させるなど、生活していく上で欠かせない物質です。
セロトニンが不足すると『不安・恐怖・イライラ・キレやすい』が起こります。
自分ではそんなつもりもないのに、ついついイライラ・・・もしかしてセロトニン不足かも?
☆冬うつを軽減させる5つの対策
1.温める(朝シャワー)
2.太陽光を浴びる(日光浴)
3.リズム運動で筋肉をほぐす⇒セロトニン分泌
4.セロトニンウォーキング
5.寝る前にはちみつ入りホットミルクを飲む
1.温める(特に朝シャワー)
夜入るなら、湯船で全身浴(夜の半身浴は緊張させてしまう)。
遅く帰ってきた日は、サッサと寝て、熱めの朝シャワーがオススメ。
ふくらはぎ、お尻(仙骨・臀部)、お腹、背骨(首の下。下を向いたときに、出っ張る部分)を重点的に温めるだけで、すぐに目が覚めてきます。
2.太陽光を浴びる(日光浴・これが一番効きます!)

太陽光を浴びることでメラトニンが減少して、セロトニンが分泌されスッキリします。
太陽光を浴びることで、約14〜15時間後にメラトニンの分泌が開始されます
太陽光が入るようにカーテンは開けたまま(レースのカーテン)、できれば窓際で寝る。
朝日が出ている日は、30分ほど日光浴をする。
起床時に室内の電気をつけてもいいですが、太陽光に比べると光量が足りません。
晴れの日は 10万ルクス
曇りの日 1万ルクス
一般家庭の室内 300〜400ルクス
いかに太陽の光が強い刺激なのかわかるかと思います。
また日光浴をすると皮膚の下ではビタミンDが生成されて、骨もしっかりして、美肌もまちがいなし。
紫外線を避けすぎて、美白を追求しすぎると、身体は弱ってしまいます(^_^;)
何事もバランスが大事ですね。
3.リズム運動で筋肉をほぐす⇒セロトニン分泌
上下振動を使って、全身の筋肉をほぐしましょう。
セロトニンは太陽光だけではなく、一定リズムの刺激によっても分泌が促進されます。
1.両足を肩幅に開いて立ち、親指を握るように両手を組んで、両腕をおへその前に置く。
2.膝のクッションを効かせて、 全身をプルプルと上下に振動させるだけ。 自分が心地よく感じるリズムとスピードで。
3.最初は3分からはじめて、慣れてきたら、6分、9分、12分と3の倍数で増やす。
バランスボールの上に座って、ボヨンボヨンと上下に動くだけでもいいです。
4.セロトニンウォーキング
通勤ついでにリズム運動です。
一歩(吐いて)
二歩(吐いて)
三歩(吸って)
四歩(吸って)・・・・・・
ハッハッ、スッスッ
このように呼吸と歩行のリズムをあわせるだけです。
15〜20分以上続けると、セロトニンの分泌が促進されます。
呼吸は鼻呼吸がいいでしょう。
電車通勤の方は、これを習慣にするとよいでしょう。
5.寝る前にはちみつ入りホットミルクを飲む
牛乳に含まれるトリプトファンというアミノ酸がセロトニンの原料になります。
ブドウ糖はトリプトファンの吸収を助けます。
ただし、牛乳の飲み過ぎは腸の調子を悪くするので、睡眠前のカップ1杯にしておきましょう。
豆乳もいいようですが、牛乳のアロマ効果(赤ちゃんの頃を思い出す??)があるので、こちらをオススメします。
電子レンジで温めたら、すぐにできますね(^ω^)
冬うつと腸内環境
突然ですが、砂糖か小麦(パン・麺・パスタ)を多く摂っていませんか?
冬うつの原因の一つが『腸内環境の乱れ』です。
砂糖、もしくは小麦を多く摂っている食生活ですと、確実に胃腸の消化機能は落ちてきます。
機能が落ちるとリズムも乱れて、神経的な症状や脳の誤作動によるホルモンバランスの乱れで、冬うつの症状がでてきます。
まずは砂糖、もしくは小麦をたくさん摂っていないかをチェックしましょう。
もし、摂っている生活でしたら、主食から抜きましょう。
料理に砂糖は使わず、主食もご飯のみに変えます。
これだけでもかなり症状の改善が期待できます。
治しすぎにご注意を
冬うつは治しすぎて、思いっきり元気になりすぎると、夏に元気がなくなるのをご存じでしたか?
冬うつの原因の一つに『リズム感の乱れ』があります。
身体のリズム(血流・リンパ液・腸内・自律神経)が乱れることで起こります。
だからといって、すごーーーく調子をよくしすぎると、夏のリズムが乱れ、夏バテの原因に。
今の日本は、特に会社員をしている方は、1年中『平均的に働く』ことを求められていますよね?
四季がハッキリしているので、日本で暮らしていたら冬は少々落ち込むぐらいが普通です。
そこをどうにか、平均にあげようとがんばってしまうのは危険です。
冬うつで、仕事や生活に支障が出過ぎて、問題だらけでしたら治療が必要です。
少々の問題はあっても、動けるぐらいなら、春になったら、元気になるかなぁぐらいに構えていても問題ありません。
今の生活と身体をどこら辺で折り合いをつけるか?
そこが冬うつ治療の最大のポイントだともいえます。
最新記事 by 冬うつアドバイザー・松田 (全て見る)
- 冬うつ改善の3つのポイントとは? - 2017年12月3日
- 冬うつの過食を悪化させない!冬うつ対策のためにレプチン分泌を - 2017年9月22日
- 冬うつの解消にはヨガが効く!効果的なポーズは? - 2017年9月20日